

|
日本の経済制度 |
一九四〇年体制とは妙な言葉だ、と考える人もいるかもしれないが、これは、戦時体制のことである。これは、一九三〇年ころ、日本が第二次大戦に向け様々な準備をしていた時に導入された制度で、現在の日本経済の基本構造をなしているものである。
産業構造を高 度化すべき時
本論に入る前に、私たちの身近で起こっている変化の話を、パソコンを例に話してみよう。
数年前まで、研究室には日本製のパソコンがほとんどであったが、最近は外国製が増えてきている。外国のパソコンのほとんどは、アメリカ製品のものであるが、実際は、アジアで作られており、それが激しい勢いで日本のマーケットに入ってきている。昨年の統計を見てみるとパソコンの輸入が、前年に比べて七割以上も伸びてきている。ここ数年、日本の経済成長はほぼゼロ成長であるから、これは驚くべきことだ。
このように、ハイテク産業の分野において、アジアのニーズ(NIEs)諸国が伸びてきている。製造業の大量生産の分野は、もともと日本の得意分野であり、高度成長期を通じて地位を高めてきた要因であるから、これは日本に大きな影響を与えている。実はニーズだけでなく、今一番伸びているのはアセアン(ASEAN)諸国であり、新興工業国として成長してきている。
このような変化に対し、日本は産業構造を従来の構造よりも高度なものへ変え、アジア諸国の中で、適切な分業活動を進めていく必要がある。しかし、今の日本では難しい。パソコン業界をみるとそのことがよくわかる。
しばしば、現在のパソコンはWINTEL体制に支配されているといわれる。WINとは「ウインドウズ」で、パソコンを動かす基本的なソフト。TELとは「インテル」を表わしており、これはパソコンの心臓部・頭脳部にあたる演算装置「ペンティアム」を作っている会社である。
現在、日本で作られているパソコンのほとんどがこの「WINTEL」に依存せざるをえない状況である。本来であれば、このような分野に日本が入っていかなければならないのに、それができないのである。このことは、将来発展する可能性のある産業にも顕著に現われてきており、たとえば、新しい情報通信、インターネットという分野でも、リードしているのはアメリカの企業なのだ。
 |
|---|
新事業妨げる 日本の制度
なぜ、日本は新しい分野で活躍できないのだろうか。これは個人一人一人の問題ではないと私は考える。日本人は、「創造性がない」「外国の技術の模倣だけをしている」と言われるが、けっしてそんなことはないはずである。個人のレベルで見れば、創造性は世界第一級であろう。問題は、日本では、新しいアイデア・考え方を実現していくための社会的制度がないことだ。
パソコンを例に挙げるとよくわかる。パソコン産業で活躍しているアメリカの企業は、ほとんどがもともとはベンチャー企業、つまり、数人の技術者で始めたものである。例えば、マイクロソフト社のビル・ゲイツ氏も大学時代に友人と始めたものである。インターネットの「ネットスケープ」もスタンフォード大の先生ともう一人で、数年前につくった会社である。それから、情報の検索ソフトの「ヤフー」も、スタンフォードの大学院の学生が、趣味として始めたものである。
このように、少数の人間の新しい考え方が、そのまま事業化するような仕組みがアメリカの場合には非常によく機能しているのだ。
ところが、日本の場合、特に、パソコンを製造している会社はほとんど例外なく大企業である。アメリカの場合、昔からの大企業は、おそらくIBM一社である。
なぜこのような差がでてきたのか。いくつかあると思うが、特に重要な二つの理由を挙げてみる。
一つは、日本の企業の仕組みである。日本の大企業では、終身雇用制、年功序列が普遍的にみられる仕組みであるが、この中で新しい事業をやろうとして企業から飛出すのは、あまり得策とはいえない。企業の中にいれば地位も上がっていくわけで、途中で飛出すのは非常に危険なことである。また、労働市場が流動的ではないので、もし事業に失敗した場合、別の企業に入ることは難しい。
もう一つは、銀行が産業の資金を融資する、間接金融という仕組みである。もともと銀行は保守的で、安全な融資を重視する。融資先の企業が成長しようがしまいが、あまり重要ではなく、リスクのある分野に対してはなかなか資金を供給できないのである。
ところが、アメリカは、さきほど述べたベンチャー的な企業の多くは、ほとんどが直接金融である。企業が社債を発行し、直接に金融市場から資金を調達する仕組みなのである。
人為的に導入 した戦時体制
実は、戦前日本では企業の構造、労働者の企業間の移動という点から言うと、労働者は、一つの企業に定着しないで、企業から企業へと移り歩くことが普通だった。それから、株主の影響が非常に大きかった。
このような体系が、戦時体制の中でかなり変わってしまった。戦争遂行を目的に、軍事産業の生産性を高めようと労働者の企業への定着を促し、職場の中での訓練を行う。もう一つは、株主の権利が制約する。これにより、企業は株式で資金を調達する仕組みから、銀行からの借入から資金を調達する仕組みになっていく。
他方、政府が積極的に金融機関の育成をする。特に、日本興業銀行をはじめとする、長期信用金庫を積極的に助成して、そこから資金供給するようにしたのである。このように金融構造を変える必要があったのは、戦時経済の要請で、経済を軍事産業に集中させる必要があったからである。
このように日本型の仕組みと考えられているのは、戦時経済の中で、人為的に導入されたものであり、これが現在にいたるまで、日本経済の中核をなしている。
それを象徴的に表わしているのが、一九四二年に制定された日銀法である。
第一条には、「日本銀行は、国家経済総力の適切なる発揮をはかるため、国家の政策に即し、通貨の調整、金融の調整、及び信用制度の保持育成を目的とする」、第二条には「国家目的の達成を使命として運営されるべし」と書いてある。経済の教科書には、中央銀行の機能は、「通貨価値の安定」となっており、日銀法はまさに40年体制そのものなのである。
高度成長支え た戦時体制
日本の高度成長の基本的な要因は様々に議論されているが、一般的には、占領軍が持ちこんできた経済の民主化政策がきっかけといわれる。
しかし、私はそれよりむしろ高度成長をなしたのは「戦時体制」だと考える。企業に対して強い帰属意識を労働者にもたらす。企業は、株主の利潤の追求ではなくて、従業員の共同体であり、企業が成長することは、株主のためではなく、自分のためになる。働けば働くほど、自分に戻ってくる、ということである。労働組合も、企業別になっており、新しい技術の導入に対して、労働組合が強く抵抗しない。日本が戦後の技術革新のたびに、上手に乗り越えてきたのは、このような企業構造が大きな要因になっている。
しかし、これは考えてみれば当然で、戦時体制は戦争の遂行という目的のために全体が協力してきた。高度成長期は、先進国という目的のために全員が協力していったのである。
体制見直し逃 した七〇年代
さて、高度経済成長は一九七〇年代の初めでほぼ終わっていく。本来であれば、その頃経済の仕組みを見直すべきだ、という議論が出たはずだった。実際に環境問題に対する関心の高まりなど、これまでの高度成長を支えてきた経済体制に批判が強くなってきたのである。何も事件が起きなかったら、おそらく経済体制が変わったであろう。
ところが、オイルショックという大きな事件が起きたのである。これにより日本経済は大混乱に陥り、経済的に生き残るのが、最優先になっていった。
ここで四〇年体制がうまく機能していくことになる。欧米諸国では、オイルショックによって、賃金が上がり、インフレ率が加速したが、日本での賃上げはゆるやかであった。それは、石油価格の上昇が賃上げに結びつかなかったからである。日本の企業は、労働者の利益共同体で、企業が潰れれば、自分も潰れてしまう。賃上げを要求することは、舟に水が入ってきて、自分もおぼれるようなことになることを知っていたからである。
このように、本来、七〇年代に変わるべき体制が変わらず、むしろ日本人は四〇年体制に自信をもってしまったのである。
「競争」の評 価を変える時
話の最初に戻るが、現在、日本経済は大きな曲り角にきている。これに対する解答は経済の体制を変えていくしかない。しかし、これは難しい問題だ。単に制度の問題だけでなく、人間の考え方の問題にも影響しているからである。
典型的に現われているのは、「競争」という言葉に対する評価である。日本人の多くの人は、「競争」というのをあまりよく思っておらず、それより「協調」が望ましいと考えている。どちらが良いかは一概には言えないが、本来「競争」が必要とされる分野にも、協調が言われていることが問題である。
今は、高度成長の時のように目的がはっきりしていない。一つの目標にむかって全員でやっていく、という感覚とは大きく違う。試行錯誤の過程が必要な時である。「競争」という言葉に対する考え方、これを変えていかなくては、今の閉塞的な状況は抜け出せないであろう。
(文責編集部)
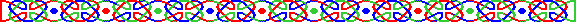
「巨石遺構の築造」
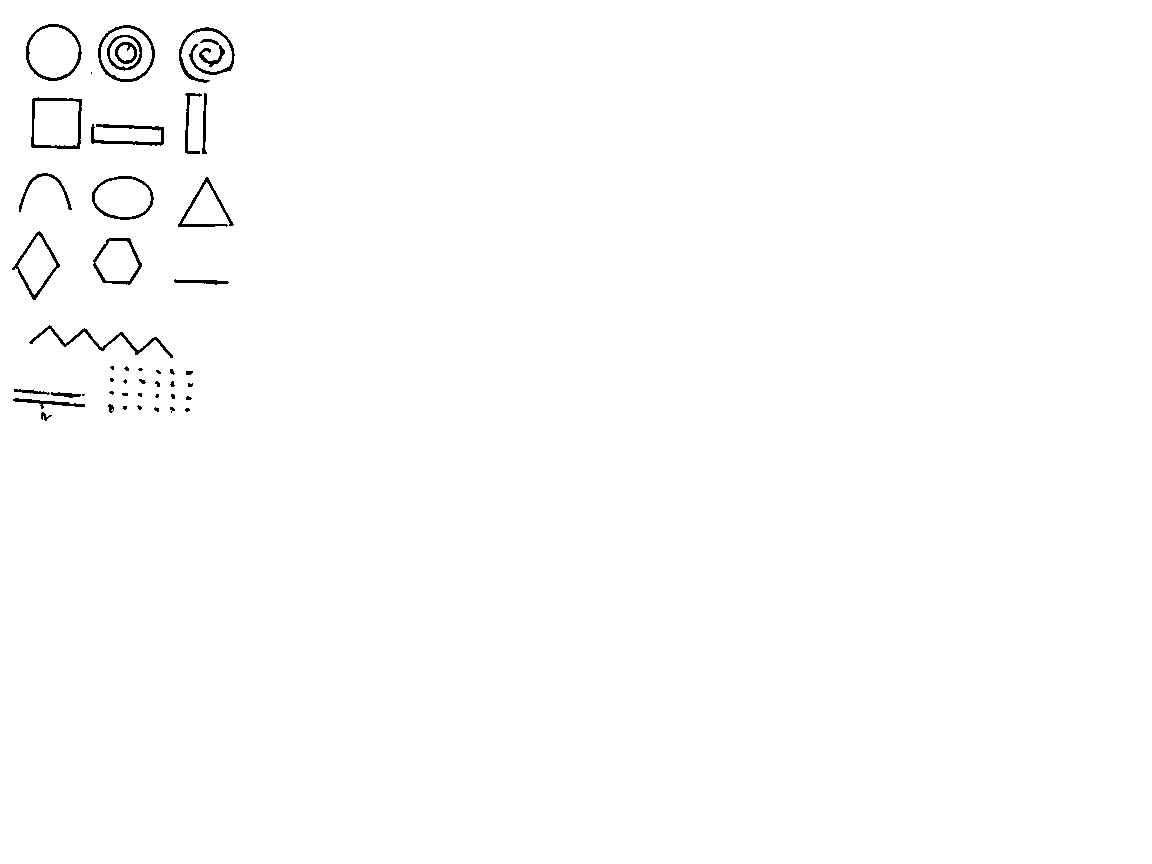
|
|---|
巨石記念物に 見られる特徴
巨石文明を代表するメンヒル、ドルメン、アリニュマン、及びストーンサークルに見られる特徴を次に書き出しておこう。
(1)石
・人(man/men)を表わす
巨石
・人、巨石、サタンを表わす
・男女石
(2)蛇の形状、紋様
※右図参照
(3)サタンと関連する事項
1 巨石信仰
2 巨石虐殺
3 巨人信仰
4 蛇信仰
5 男根崇拝
6 宇宙卵(蛇か鳥の卵)
7 墓―死と再生
8 聖ミカエル、聖ジョージ
9 古代ブリテン人
10 ドルイド
(4)高度な幾何学、暦学、天文学、地球物理学などの知識と、計算し尽くされた設計。超常力によらなければ不可能な設置場所の選定。
・地球が完全な円ではないこと、太陽の周りを廻る地球の軌道が楕円であることを知っていた。分岐点を記録する際、標識を零点から約〇・五度離して設置することを知っていた。
・真正の円ではなく、全てが楕円(蛇や鳥の卵の形)で表現されている。
・直角三角形を使った楕円の描き方
・一年の長さを十六か月に等長に区分
・太陽、月、食などの天体観測(ロクマリアケ、ストーンヘンジ)、日時計(ニューグレンジ)、巨石図表(カルナック)
・ストーンヘンジの地球上における位置―あるべき一点に置かれた。
・ストーンヘンジのサルセン円の石の影の位置―全てが計算されていた。
・巨石遺構は地下水脈や地下断層があるらしい所に設置されている。
(5)上空からしか展望できない広大な構図―上空から見て、初めて印象的(カルナック、ストーンヘンジ、エイバリー)―上空からブループリントを描いたのであろう。
(6)魔術が取り沙汰される程の巨石運搬力、高度な建築技術、指導力
(7)世界共通の長さの単位の使用(巨石ヤード、巨石ロッド)
(8)世界各地に散在しているが、大平原や山中、海岸など、都会を離れた広大な地域に存在し、一地方ではごく局所的にかたまって見られる。
(9)同一目的のためになされた長期的建設―ストーンヘンジⅠ、Ⅱ、Ⅲは四期にわたり、千七百年の間に別々の民族によって建設されている。背後の指導者は、同一人物であるはずだ。
文字による記録がない。突然現われたごとくに、巨石建造物が出現している。
建造目的も、用途も不明(実際には、様々な用途に使われてきた―墓、寺院、日時計、天文台、治癒、豊穣など)
印象
・壮大、雄大
・整然、崇高、厳粛
・異様、凄味、無意味、超常性
・素朴、たくましさ、したたかさ
巨石の築造を指 導する霊的存在
ここにまとめた巨石記念物と、その建造状況の特徴から帰納されるものは何であろうか。それらの構築を意図した者は、地上に永遠に残る素材である石を用いて、幾つもの民族と多くの世代を指導しながら、全世界のあちこちに蛇の形状で表現されている巨石遺構を、根気よく建造し続けたのである。そのそこここに蛇紋様を刻み込ませた。この紋章の持主は、宇宙の天体と地球の構造について知り抜いている者、幾何学、天文学、暦学、地球物理学などの知識と実際について、現代の科学者以上の力量を持つただならぬ者、天体と地球を大いなる宇宙空間から眺めて設計図を引き得る場にある存在、地球内部を透視することができる霊的存在、そして霊力を行使して地上の人間を操作し、巨石遺構の築造を指導できる霊界の存在である。
巨石文明の背後 にあるサタン
蛇の印をもつこの霊的存在は、宇宙人でも他の人類でもない。それは創造主の片腕となって宇宙創造を手伝った者、神に次いで年老いた者であり、今なお神から奪い取った世界と人間を永遠に私物化せんと企んでいる者、あのサタン以外の者であり得ようはずがない。巨石の虐殺に見られるように、キリスト教徒たちは異教徒が築いたエイバリーの巨石遺構が、サタンにまつわるものであることを知っていた。この霊的存在は容易に文字を創り、教える力を持ちながら、文字による記録を残すことをあえて避けてきた。サタンが巨石文明の指導者であるという証拠は、何としても残すわけにはいかなかったからである。このことは、世界の多くの古代文字が、未解読のままである事実と関わりがあるように思われる。巨石文明の背後に控えているサタンを証す記述をした者は、おそらく部族もろとも抹殺されてしまったに相違ないことをうかがわせる。天文学に秀でていたドルイド僧の間では、文字による記述は一切許されていなかったという。それにしても、蛇の形状をした土手と堀に囲まれた聖なる森における彼らの祭壇の設置状況は、巨石遺構のそれと、よく符合しているのである。
 t-shinpo@super.win.or.jp
t-shinpo@super.win.or.jp