| ホームページ紹介 Vol.33 |
海洋研究会は、伊豆諸島や小笠原、西表島で活動するスキューバダイビングのサークルだ。活動としては、毎週木曜日、午後8時から9時まで、本郷二食下プールにて練習(スキンダイビング)を行っている。合宿は年に7回程度行っており、夏には2週間以上の大規模な合宿を行う。今年は、沖縄西表島に行くという。1年生の1年間での平均スキューバ本数は40本くらいになる。
スキューバダイビングをするには、買うと十数万円するようなBC・レギュレータなどの「重器材」が必要だが、当サークルではこれらを所有、維持管理しているため、年間5千円程度の年会費を払えば使うことができるという。
入会資格としては、3年生の夏合宿までのすべての練習や合宿に参加できることが条件であるという。上級生が指導するスタイルを取っており、安全を確保するためにこのような条件が必要であるらしい。そのため、年間の新入部員は10人程度で打ち切っている。
当サークルは、1969年に、東大の研究機関「海洋研究所」の有志で結成されたことに発端がある。当時は、「スキューバ」という名称が普及しておらず、「アクアラング」と呼んでいた時代で、初めのころの活動は、スキンダイビング(いわゆる素潜り)のみであったという。海洋研究会といってもいわゆる「学術研究」をやっているわけではなく、名称が覚えやすく、呼びやすいために使われているということだ。
ホームページには、フォトギャラリーやダイビングについてのFAQ集、さらにはダイビング運を占う「だいぶおみくじ」まであるので、いろいろ楽しめる。
| 書 評 |
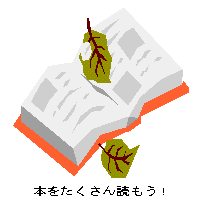
著者がオウム事件から学んだことは、「自己や、社会や、世界について考えるときに、いまここで生きている自分のあり方を、けっして棚上げにしないような思想の重要性」だという。つまり、自分を傍観者という安全地帯において、遠くからオウムのことをあれこれ断罪しているほとんどすべての論者に、深く失望していた。そして彼らの態度は、自らの犯罪を米軍や自衛隊からの攻撃に対する防御だと正当化した、あのオウムと変わらないのではないかという疑問を投げかける。どちらも、本当に解決しなければならない問題は自分の中にあるのに、それは常に自分の外にあると言い続けているのである。そんな著者の初めてのエッセイ集。
現代の「知」には、「自分」というものを、「みずからの思想のなかに巻き込む覚悟がなければならない」とする。ものを考えることが、つねにそれを考えている自分自身の生き方へとフィードバックするような思考方法、それを著者は「生命学」と呼んでいる。そういう「知」によらなければ解決しえないような問題を現代社会は抱えているというが、逆に言うと、人間社会はもともと死体を切り刻むような分析的思考では理解できない存在なのであろう。
大学における学問は普遍性をめざすものであって、「私のためにする学問」などはないというのが基本姿勢である。それは価値と科学を分離したデカルト以来の近代の伝統でもある。しかし、そうした近代の精神が、いま人類を危機に陥れようとしている。手術は成功したが患者は死んだという愚を犯さないために、いま人類は統合的な知を必要としている。その一つの試みが、著者のいう生命学であろう。「生まれてきてやがて死んでいくこの私の生命とはいったい何か」を中心に、自然と世界を考える。ともすれば傍観者の位置に立ちたがる私たちの「知」に、強い反省を迫る書である。 (T)
(PHP研究所、本体1333円)
ヘルマン・ヘッセがスイス南部テッスィーン州の山村モンタニョーラに移り住んだのは1919年。家族をドイツに残しての独り暮らしであった。以後、1962年に亡くなるまで43年間、この地を愛し、ここに骨を埋めた。イタリアに近い南欧の村である。その生活ぶりは既刊の『庭仕事の愉しみ』に詳しい。ヘッセは著作と同じか、あるいはそれ以上に庭仕事を愛し、家の周りのこまごまとした作業に時間を費やした。もっとも、それが独り暮らしを充実させるすべであるのは、今も昔も変わらない。
本書は、昨年がヘッセ生誕120年であるのを記念して出版されたもの。テッスィーン地方の風土、動植物、教会、民家、素朴な人々の生活、それにヘッセの日常生活や庭仕事などの趣味、読書などについてのエッセイ、詩、創作、そしてカラーの水彩画が収録されている。1946年にノベール文学賞を受賞したヘッセは、青春の苦悩を扱った『車輪の下』などの作品で日本でも広く知られている。
ヘッセの生まれ故郷はドイツ南部のナーゴルト川畔の小さな町カルフである。美しい川と黒い森(シュヴァルツヴァルト)に包まれたカルフを、後年ヘッセは「すべての町の中で一番美しい」と書くほど、愛し、懐かしんでいた。その故郷を、妻子を残して離れる決心をしたのは、第一次世界大戦中、スイスの新聞に発表した平和主義的論説で、ドイツのジャーナリズムから「裏切り者」と非難されボイコットされたため。しかし、ヘッセはドイツ人であることを捨てたのではなく、亡命してまで言説を貫くことこそ真のドイツ精神だと考えていた。
北の国から南の国へと、ヘッセの生活環境は一変した。作品に見られるプロテスタント信仰の息詰るような描写も、彼が住んだ地方の伸びやかなカトリック信仰の中でこそ書けたのではないかとも思ったりする。 (T) (草思社、本体2500円)